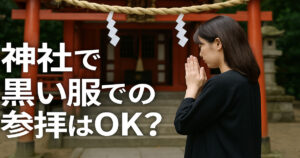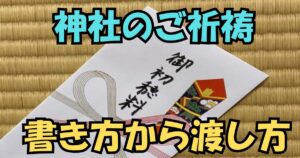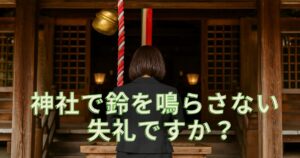神社に参拝する際、手水舎で手や口を清めることは大切な作法のひとつです。しかし、「神社 口をすすぐのはなぜ必要なのか?」「手水舎の正しい作法とは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
手水舎(ちょうずや・てみずや)は、参拝前に心身を清めるための神聖な場所です。そこで手を洗うことには、単なる手洗い以上の意味があり、穢れを祓うという重要な役割を持っています。また、神社で手を洗うところに花が飾られる「花手水」や、龍があしらわれている手水舎の由来についても気になる方がいるかもしれません。
さらに、神社で口をすすぐ際の作法や、適切な吐き出す場所について知らないと、他の参拝者に迷惑をかけてしまう可能性もあります。参拝前に手を洗う水が流れる理由や、口をすすぐ意味を理解することで、より丁寧な参拝ができるでしょう。
一方で、衛生面が気になって「神社 口をすすぎたくない」と感じる方もいるかもしれません。その場合の対応方法や、神社の手水舎を忘れたときの対処法についても解説します。
本記事では、正しい手洗いと口すすぎの方法を詳しく解説し、参拝の心を整えるためのポイントを紹介します。神社での手水作法を学び、より敬意をもって参拝できるようにしましょう。
- 神社で口をすすぐ作法とその意味
- 手水舎で手を洗う理由と正しい手順
- 口をすすぐ際の注意点と適切な吐き出し場所
- 口をすすぎたくない場合の対応方法
神社で口をすすぐのはなぜ?意味と作法を解説

- 神社の手水舎 手を洗うところ 名前読み方 てみずや ちょうずや どっち?
- 神社で手を洗う場所の意味とは?
- 神社で手を洗うところに花がある理由
- 手水舎の龍は何を意味する?
- 神社で口をすすぐとき、吐き出す場所は?
手水舎の読み方|てみずや?ちょうずや?
神社にある手水舎(ちょうずや、てみずや)は、参拝前に手や口を清める場所です。どちらの読み方も正しいですが、「ちょうずや」と読むことが一般的です。
この名称は、古来より使われてきた「手水(ちょうず)」という言葉に由来します。「手水」は、神道における禊(みそぎ)を簡略化したもので、参拝前に身を清めるために行います。一方で、「てみずや」とも読まれるのは、漢字の「手水」を「てみず」と読むことからきています。
地域や神社によって呼び方が異なる場合もありますが、どちらの読み方でも意味は同じです。参拝の際には、この手水舎で心身を清め、神聖な場所へ進む準備をしましょう。
 黒猫
黒猫いきなり読める人なんていないよ



「てみずや」「ちょうずや」が一般的みたい
神社本庁では「てみずや」、大國魂神社では「てみずしゃ」の表記だとか
手を洗う場所の意味とは?


神社の手水舎は、単なる手洗い場ではなく、心身を清めるための神聖な場所です。
神道では、穢れ(けがれ)を祓い、清らかな状態で神様にお参りすることが重要とされています。そのため、手を洗う行為は、物理的な汚れを落とすだけでなく、精神的な穢れを払う意味も持ちます。また、昔は川や井戸の水で身を清めてから神社に参拝する習慣がありましたが、現在ではその代わりとして手水舎が設置されています。
手水舎で手を洗うことは、神様に対する敬意を示す行為です。しっかりと作法を守りながら、心を落ち着けて清めるようにしましょう。
花がある理由


神社の手水舎に花が飾られているのを見たことがあるかもしれません。これは「花手水(はなちょうず)」と呼ばれるもので、美しい彩りとともに神聖な場所をより清らかにする目的があります。
花手水が始まったのは比較的最近のことで、特にインスタグラムなどSNSの普及とともに広まりました。しかし、もともと神道では「清浄さ」が大切にされており、花もまた神聖なものと考えられています。そのため、手水舎に花を浮かべることで、参拝者の心を和ませると同時に、神聖な場の清めにもつながるのです。
また、季節の花が使われることが多いため、訪れるたびに異なる風情を楽しめるのも魅力の一つです。手水舎を利用する際には、花の美しさを味わいながら、心を落ち着けて清めるとよいでしょう。
龍は何を意味する?


手水舎に龍の像や蛇口があるのを見かけたことはありませんか?これは、神社において龍が「水の神」として信仰されているためです。
龍は古くから水を司る神聖な存在とされ、雨を降らせ、川や湖を守る役割を担うと考えられてきました。そのため、手水舎に龍の姿があるのは、参拝者が清らかな水で身を清める場を守る象徴としての意味が込められています。
また、龍は「力強さ」や「繁栄」の象徴でもあり、神社の守護としての役割も持っています。手水舎で水を使う際には、龍の姿を見ながら、水の恵みに感謝する気持ちを持つことも大切です。
吐き出す場所は?
神社での口のすすぎ方には正しい手順があります。これは、神前での参拝を行う前に心身を清めるための大切な作法です。間違った方法で行うと、他の参拝者に迷惑をかけたり、神聖な場にふさわしくない行為とみなされることがあります。
まず、柄杓(ひしゃく)を右手で持ち、水を汲みます。この際、一度だけ水を汲み、その水で手と口を清めることが重要です。
次に、左手を清めます。汲んだ水を左手にかけ、しっかりと洗い流しましょう。
その後、柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。同様に水をかけて洗います。
続いて、再び柄杓を右手に持ち、左手のひらに水を受けて、口をすすぎます。このとき、柄杓に直接口をつけるのは厳禁です。水を口に含んだら、静かにすすいで吐き出します。周囲の人への配慮として、左手で口元を隠しながら行うのが望ましいでしょう。
口をすすいだ後は、もう一度左手を洗い流し、最後に柄杓の持ち手部分を清めます。残った水を柄杓の柄(持ち手)に流し、清めたうえで、元の位置に伏せて戻しましょう。
この一連の動作を丁寧に行うことで、参拝の準備が整います。神社の境内は神聖な場所であるため、正しい作法を守りながら心を込めて手水をとりましょう。
神社で口をすすぐ作法と注意点
- 神社で参拝前に手を洗う水はなぜ流す?
- 神社で口をすすぐのはなぜ必要?
- 神社で口をすすぎたくない場合の対応
- 神社の手水舎を忘れたときの対処法
- 正しい手洗いと口すすぎで参拝の心を整える



動画で流れを把握するといい、頭じゃなく体で覚えればいいの
東京都神社庁 公式チャンネル
[神社参拝の作法]手水の仕方



ゆっくりとした感覚。佇まいって言うのかな?
美しくて魅入るね
参拝前に手を洗う水はなぜ流す?
神社の手水舎で手を洗う際、流れる水を使うのには深い意味があります。単に手を洗うためだけでなく、神道における清めの考え方に基づいているのです。
古くから日本では、水には浄化の力がある と考えられてきました。川や滝の流れる水に身を浸して心身を清める「禊(みそぎ)」という儀式がその代表例です。手水舎の水もこの考えに基づいており、流れる水を使うことで、手や口だけでなく、心まで清める意味を持っています。
また、一度使った水を再利用しないことで、穢れ(けがれ)を流す という意味もあります。もし水が溜まったままの状態であれば、一度清めた手や口に再び汚れがついてしまうかもしれません。そのため、手水舎の水は常に流れ続けていることが望ましいのです。
このように、流れる水を使うことには、心身を清めるための重要な意味があります。手水をとる際には、ただ手を洗うだけでなく、水の流れに込められた意味を意識しながら行うと、より丁寧な参拝ができるでしょう。
口をすすぐのはなぜ必要?
神社で口をすすぐ行為には、単なる衛生的な目的以上の意味があります。これは、神道における「清め」の考え方に基づく大切な作法のひとつです。
まず、口をすすぐことは「言葉の穢れを祓う」ために行われます。日常生活では、無意識のうちに悪口を言ったり、不平不満を口にすることがあります。口をすすぐことで、そうした穢れを清め、神様の前で心を整えるのです。
また、神前での祈りや願い事は「言葉」によって伝えるもの です。清らかな状態で言葉を発するためには、口を清めることが必要だと考えられています。
さらに、手水は古代の「禊(みそぎ)」の簡略化された形 です。かつては川や海で全身を清めてから神前に立つのが正式な作法でしたが、現代では手水舎で手と口を清めることで、その代わりとされています。口をすすぐことも、心身を清める行為の一環なのです。
このように、口をすすぐことには神聖な意味が込められています。手水舎を利用する際は、その意義を理解し、丁寧に作法を行いましょう。
口をすすぎたくない場合の対応


神社での手水の作法では口をすすぐことが推奨されていますが、衛生面や個人的な理由で抵抗を感じる方もいるかもしれません。そのような場合でも、作法に配慮しながら対処する方法があります。
まず、口をすすぐ代わりに、唇を軽く湿らせるだけでも構いません。左手に受けた水を口元に運び、実際にすすがなくても「清める意識」を持つことが大切です。
また、水を口元に近づけるだけの方法もあります。水を口に含まず、左手の水をそっと流すことで、清める意図を示すことができます。
どうしても口をすすぐことに抵抗がある場合は、心の中で清める意識を持つことも重要です。水を使わなくても、手を合わせて「口を清める気持ち」を込めるだけで、最低限の作法を守ることになります。
ただし、神社によっては、正式な作法として口をすすぐことが求められる場合があります。そのため、訪れる神社の方針を確認し、可能な限り作法を守るように心がけるとよいでしょう。
このように、口をすすぐことが難しい場合でも、別の方法で清める意識を持つことが大切です。参拝時には、周囲の状況を考慮しながら、自分に合った方法を選びましょう。
手水舎を忘れたときの対処法
神社の参拝前に手水舎で手や口を清めることは基本の作法ですが、うっかり忘れてしまった場合、焦る必要はありません。手水舎を使わなかったからといって参拝ができなくなるわけではなく、代わりの方法で心を整えることができます。
まず、手水舎に戻れる場合は、できるだけ戻って手を清めるのが理想的 です。参拝の前に身を清めることは大切な儀式の一つなので、可能なら正しい手順で行いましょう。
もし手水舎に戻れない場合や、手水舎がない神社では、持参した水で手を清める という方法があります。ペットボトルや水筒の水を手に注ぎ、神社の作法と同じ手順で手を洗い、口をすすぐことで代用できます。ただし、他の参拝者の迷惑にならないよう、静かに行うことが大切です。
また、ウェットティッシュやおしぼりを使うのも一つの方法 です。手水の本来の目的は「清めること」なので、流水でなくても手を拭くことで心を整えることは可能です。特に寒い時期や衛生面が気になる場合は、ウェットティッシュを持参すると便利です。
さらに、古くから伝わる方法として「草手水(くさちょうず)」 があります。これは、境内の草や葉を軽く手に当て、手をなでることで清めるという方法です。実際に水を使わずとも、清める意識を持つことで代用できると考えられています。同様に、雪が積もる地域では「雪手水(ゆきちょうず)」 といって、雪を手に取って清める方法もあります。
もし何の準備もできない場合は、心の中で「清める意識」を持つことも大切 です。深呼吸をして気持ちを整え、静かに手を合わせるだけでも心の浄化につながります。
このように、手水舎を忘れてしまった場合でも、代替の方法はいくつかあります。大切なのは、形式ではなく「清める気持ち」を持って参拝することです。
正しい手洗いと口すすぎで参拝の心を整える
神社の参拝において、手洗いや口すすぎは単なるマナーではなく、神様に敬意を表し、心を清めるための重要な作法です。この行為を丁寧に行うことで、より気持ちを込めた参拝ができます。
まず、手水の基本的な流れを理解することが大切 です。神社の手水舎では、柄杓を使って一度だけ水を汲み、その水で手と口を清めます。
- 右手で柄杓を持ち、水を汲
- 左手に水をかけて清める
- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清める
- 再び柄杓を右手に持ち、左手のひらに水を受けて口をすすぐ
- 口をすすいだ後、もう一度左手を清め
- 最後に柄杓の柄を清めて元の位置に戻す
この一連の流れを落ち着いて行うことで、神前に立つ準備が整います。
また、手水を行う際には心の持ち方も重要 です。ただ作法に従うだけではなく、参拝する神社の神様に対して敬意を持ち、感謝の気持ちを込めることが大切です。
さらに、口をすすぐことには「言葉の穢れを祓う」という意味があります。日々の生活の中で、不平不満や悪口を口にすることは避けられません。口をすすぐことで、それらを清め、神様に対して清らかな気持ちでお参りできるのです。
一方で、正しい手水の作法を知らないまま行ってしまうと、無意識のうちにマナー違反となることがあります。例えば、柄杓に直接口をつけたり、すすいだ水を手水舎の水盤に吐き出すのは避けるべき行為です。他の参拝者も気持ちよく利用できるよう、作法を守りながら行いましょう。
このように、手水を正しく行うことは、単なる作法ではなく、参拝の心を整えるための大切な儀式です。手や口を清めながら、神様に対して誠実な心で向き合うことを意識すると、より深い参拝ができるでしょう。
神社で口をすすぐ作法の意味と正しい参拝方法


- 神社の手水舎は「ちょうずや」「てみずや」と読む
- 手水舎は参拝前に身を清めるための重要な場所である
- 神社 口をすすぐ行為には言葉の穢れを祓う意味がある
- 龍が設置された手水舎は水の神としての象徴である
- 口をすすぐ際は柄杓に直接口をつけてはいけない
- すすいだ水は手水舎の排水溝や砂利の上に静かに吐き出す
- 参拝前に水を流すのは穢れを洗い流すための儀式である
- 花手水は神聖な空間を彩り、清浄な雰囲気を演出する
- 口をすすぎたくない場合は、唇を湿らせる方法がある
- すすぐのを忘れた場合は、心を整えて参拝すれば問題ない
- 手水舎を忘れたときは、持参した水やウェットティッシュで代用できる
- 草手水や雪手水は、古くから伝わる清めの方法の一つである
- 正しい手水作法を行うことで神様への敬意を示せる
- 口をすすぐ作法を守ることで、より格式ある参拝ができる
- 参拝の作法を学ぶことで、神社での礼儀を正しく理解できる